橈骨遠位端骨折リハビリの進め方と注意点を解説!
- 2025年06月20日
- カテゴリー:骨折

橈骨遠位端骨折は、手首を骨折した際に最も多く見られる骨折のひとつです。骨がくっついても、手首の可動域や筋力の回復にはリハビリが欠かせません。本記事では、橈骨遠位端骨折後のリハビリの流れ、回復までの期間、日常生活での注意点などをわかりやすく解説します。これからリハビリを始める方や、回復に不安を感じている方に役立つ内容です。
目次
1.橈骨遠位端骨折とは
- 1-1:橈骨遠位端骨折の基本的な解説
- 1-2:どんな人がなりやすい?主な原因と発症リスク
2.リハビリの開始時期と全体の流れ
- 2-1:いつからリハビリを始める?手術・保存療法別の目安
- 2-2:回復までの3ステップ(急性期・回復期・維持期)とは
3.実際のリハビリ内容
- 3-1:初期に行う運動療法とストレッチ
- 3-2:中期〜後期にかけての筋力トレーニングと機能回復
4.日常生活での注意点
- 4-1:家事・仕事・育児への影響と工夫
- 4-2:再発を防ぐための生活習慣と予防策
5.よくある質問と不安解消Q&A
- 5-1:痛みがなかなか引かないのはなぜ?
- 5-2:完治するまでどれくらいかかる?年齢別の目安
1.橈骨遠位端骨折とは
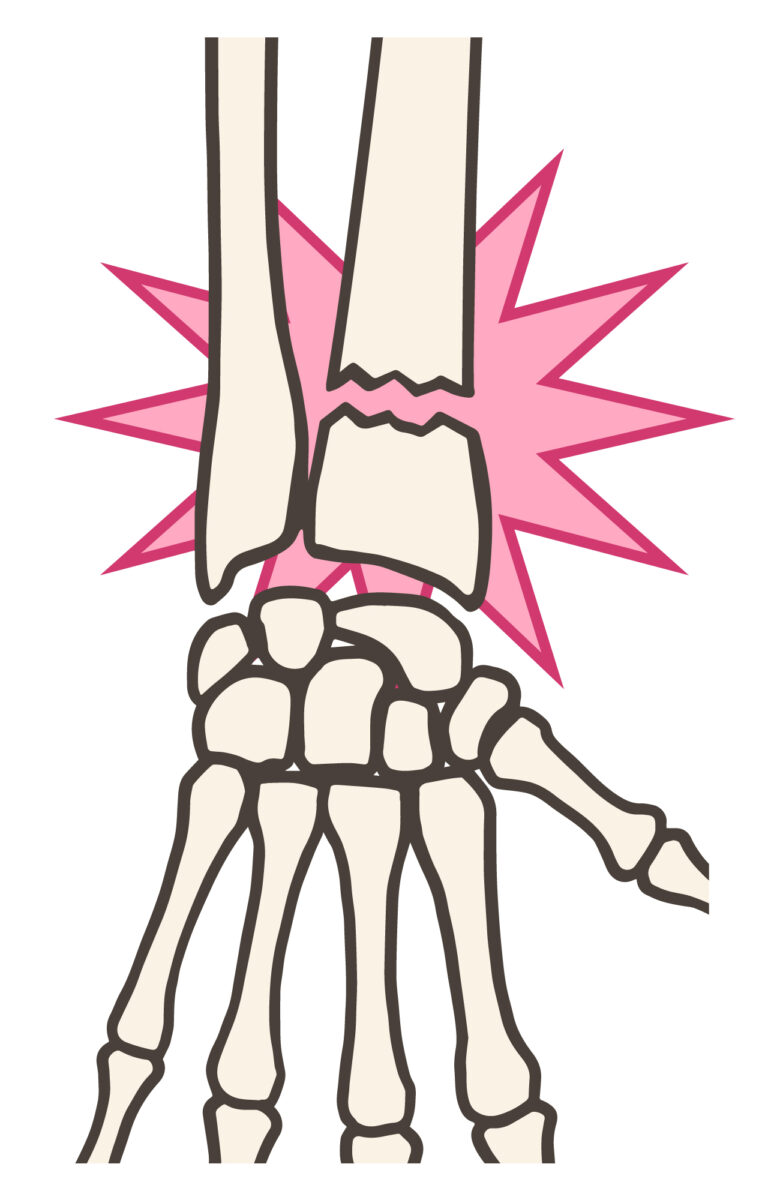
1-1:橈骨遠位端骨折の基本的な解説
橈骨遠位端骨折は、手首付近の橈骨という骨の先端部分が折れるケガです。転倒時に手をついてしまった際などによく起こり、高齢者や女性に多く見られます。骨折の程度やズレの有無によって、手術を行う場合と保存療法(ギプス固定など)で済む場合があります。見た目に腫れや変形が現れることもあり、早期の診断と適切な治療が重要です。治療後は、骨が癒合しても手首の柔軟性や筋力が低下するため、リハビリが欠かせません。
1-2:どんな人がなりやすい?主な原因と発症リスク
この骨折は、特に60歳以上の女性に多く見られます。加齢とともに骨密度が低下し、骨がもろくなることで、ちょっとした転倒でも骨折しやすくなるためです。また、スポーツや自転車事故、雪道での転倒などでも若年層に発生することがあります。骨粗しょう症、筋力の低下、反射神経の衰えなどがリスク要因です。日頃からの転倒予防や骨の健康維持が発症リスクを下げるポイントとなります。
2.リハビリの開始時期と全体の流れ
2-1:いつからリハビリを始める?手術・保存療法別の目安
リハビリの開始時期は、治療法によって異なります。手術を受けた場合、固定期間が短いため比較的早期(術後数日〜1週間程度)にリハビリが始まります。保存療法(ギプス固定)の場合は、骨がある程度くっつくまでリハビリを控える必要があり、通常は3〜6週間後から開始します。ただし、指の運動や肩・肘の可動域を保つ運動は早期から行うことが推奨されています。医師や理学療法士の指示に従うことが大切です。
2-2:回復までの3ステップ(急性期・回復期・維持期)とは
リハビリは「急性期」「回復期」「維持期」の3段階に分かれます。急性期(受傷後1か月程度)は固定中で、痛みを避けながら指の可動域や肩の動きを維持することが中心です。回復期(受傷後1~3か月)ではギプスや装具を外した後、手首や前腕の可動域訓練や筋力強化を進めます。維持期(受傷後3か月以降)は、日常動作に近い運動を取り入れながら、元の生活への復帰を目指します。各段階での目標と方法を理解し、段階的に進めることが回復の鍵となります。
3.実際のリハビリ内容

3-1:初期に行う運動療法とストレッチ
初期(急性期)は、骨の癒合を妨げない範囲で軽い運動を始めます。指や肩を動かすことで、関節の拘縮(かたまり)を防ぎ、血流を促進します。たとえば、手をグーパーさせたり、肩周りの筋肉をほぐす事が重要です。他の関節の柔軟性を維持することに集中し、痛みが強い場合は冷却や安静を優先します。
3-2:中期〜後期にかけての筋力トレーニングと機能回復
中期(回復期)になると、可動域訓練と筋力トレーニングを本格的に行います。手首の回旋運動、手を反らす・曲げるといった動きの訓練が中心です。さらに、ゴムボールを握ったり、ゴムチューブを使って前腕筋を鍛えるなど、筋力回復のためのトレーニングも取り入れます。後期(維持期)では、ドアノブを回す、タオルを絞るなど、日常生活に近い動作を再現する運動が中心になります。これにより実生活へのスムーズな復帰が目指せます。
4.日常生活での注意点
4-1:家事・仕事・育児への影響と工夫
骨折後は日常生活にさまざまな支障が出ます。特に利き手をケガした場合、食事、歯磨き、着替え、スマホ操作などが困難になります。家事や育児では片手で作業せざるを得ないことが多く、無理をしないことが大切です。食器は軽い素材に替えたり、調理は電気調理器などを使って負担を減らすと良いでしょう。職場復帰も、書類作業や重い物の持ち運びなどは無理を避け、必要に応じて業務の調整をお願いしましょう。
4-2:再発を防ぐための生活習慣と予防策
回復後も、骨折の再発リスクには注意が必要です。特に骨粗しょう症が原因の場合、再発しやすいため、定期的な骨密度検査やカルシウム・ビタミンDの摂取が効果的です。また、筋力を維持するための軽い運動やストレッチを習慣づけることも大切です。自宅の段差や滑りやすい場所には手すりや滑り止めを設置するなど、転倒リスクを減らす工夫も再発予防には有効です。
5.よくある質問と不安解消Q&A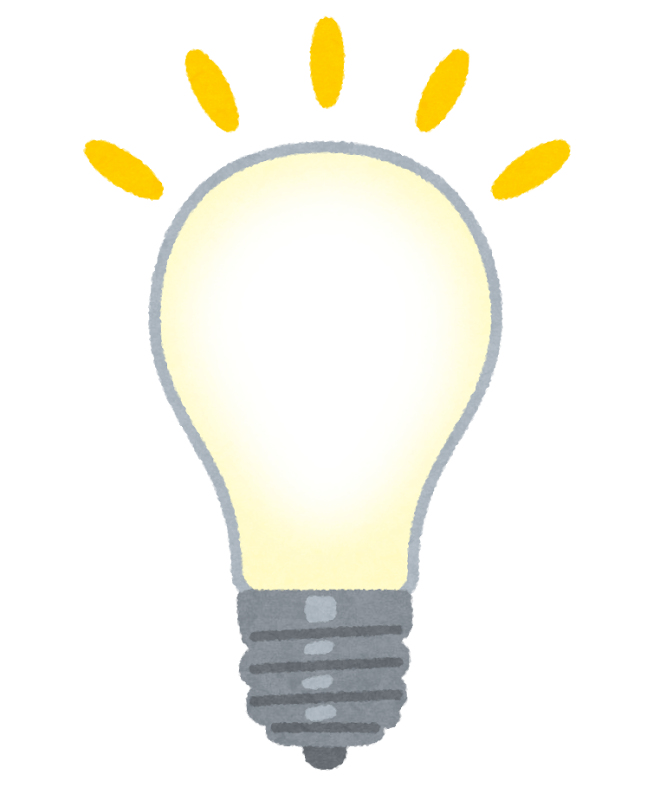
5-1:痛みがなかなか引かないのはなぜ?
骨が癒合しても、関節の硬さや筋肉の緊張が原因で痛みが続くことがあります。特に動かすときに痛みが出る場合は、可動域制限や筋力低下が関係している可能性があります。また、手術後のプレートやボルトが神経を刺激しているケースもあります。痛みが強い、長引く場合は、再度整形外科を受診し、レントゲンや診察を受けることが重要です。自己判断でリハビリを中断するのは避けましょう。
5-2:完治するまでどれくらいかかる?年齢別の目安
回復期間は年齢や治療内容によって異なりますが、一般的には骨癒合までに約6〜8週間、その後のリハビリを含めて3〜6か月程度が目安です。若年層であれば回復が早く、日常生活への復帰もスムーズですが、高齢者では骨の回復が遅れやすく、リハビリにも時間がかかる傾向があります。無理をせず、段階的に負荷を上げることが、長期的な回復と再発防止に繋がります。
【まとめ】
・加齢により骨が脆くなり、手をつくように転ぶと手首が骨折する
・骨折初期は、ギブスで安静。指と肩の固さを取る事が重要。骨折中期以降は、本格的なリハビリをする。
・転倒の主な場所は自宅内が多いため、転倒予防のための工夫をする。
・痛みがなかなか引かない場合は、固さが残る・筋力が弱いなどの要因があるため整形外科に行く
いかがでしたでしょうか?
動いている以上転倒のリスクはゼロにはなりません。当院では、転倒予防のアドバイスやバランス能力の向上を目標とすることもできます。
バランス能力の要素は様々ありますが、一つに下半身の筋力が重要とされています。当院インスタグラムでは、負担の少ない筋力トレーニングもご紹介しているので是非ご覧ください。
下半身の筋力向上練習:Instagram
一度当院に来院してご自身のお身体を見つめなおしてみてはいかがでしょうか?
【簡単2ステップ予約】
①ご希望時間を選択し、お客様情報を入力し送信
②当院から当日の流れに関する事をメールにて送信致しますのでご確認ください



