胸郭出口症候群の症状を改善するリハビリとは?|専門家が教える正しい対処法

肩こりや腕のしびれ、手の冷感などが続いていませんか?それ、もしかすると「胸郭出口症候群」かもしれません。この症状は首・肩周辺の神経や血管が圧迫されることで起こり、放置すると悪化する恐れがあります。この記事では、胸郭出口症候群の基礎知識から、自宅でできるリハビリ方法までを専門家の視点でわかりやすく解説します。症状改善の第一歩として、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1. 胸郭出口症候群とは?
1-1. 症状の特徴とセルフチェック方法
1-2. なぜ神経や血管が圧迫されるのか?原因を解説
2. 胸郭出口症候群の診断と治療の流れ
2-1. 医療機関で行われる検査内容とは?
2-2. 初期治療と保存療法の基本的な考え方
3. 自宅でできる胸郭出口症候群のリハビリ法
3-1. 肩甲骨まわりのストレッチ3選
3-2. 姿勢改善に効果的なエクササイズ
4. リハビリを成功させるポイント
4-1. 痛みがあるときに避けるべき動きと姿勢
4-2. 継続するための習慣化テクニック
5. いつ病院に行くべき?受診の目安と注意点
5-1. 自宅リハビリで改善しないときのサイン
5-2. 整形外科・リハビリ科での具体的な治療法
1. 胸郭出口症候群とは?
1-1. 症状の特徴とセルフチェック方法
胸郭出口症候群は、首から腕にかけて走る神経や血管が圧迫されることで起こる疾患です。主な症状には、腕や手のしびれ、肩の重だるさ、手の冷感や力が入りづらいといったものがあります。セルフチェックとしては、腕を上げたときにしびれや痛みが強くなるかどうか、鎖骨周辺を軽く押したときに違和感があるかを確認します。
1-2. なぜ神経や血管が圧迫されるのか?原因を解説
胸郭出口症候群は、姿勢の悪化や筋肉の緊張により、神経や血管が圧迫されることが主な原因です。とくに猫背やなで肩、長時間のパソコン作業などが発症リスクを高めます。また、斜角筋や小胸筋といった筋肉が硬くなると、神経や血管の通り道が狭くなり、圧迫が生じやすくなります。日常の体の使い方が積み重なって発症するため、リハビリでは姿勢と筋肉の柔軟性改善が重要な対処法となります。
胸郭出口症候群の事をまとめた記事はこちら↓
胸郭出口症候群とは?症状・原因・自分でできるセルフチェック方法を解説 | 荒川沖姿勢改善整体アース
2. 胸郭出口症候群の診断と治療の流れ


2-1. 医療機関で行われる検査内容とは?
胸郭出口症候群が疑われる場合、整形外科や神経内科での診断が必要です。問診と身体検査に加えて、レントゲンやMRI、超音波検査などが行われ、神経や血管の圧迫の有無を確認します。また、アドソンテストやライトテストといった徒手検査によって、圧迫部位を特定することもあります。誤診を避けるためにも、似たような症状を持つ他の疾患(頸椎症など)との鑑別が重要です。
2-2. 初期治療と保存療法の基本的な考え方
胸郭出口症候群の治療では、まず保存療法が基本となります。症状が軽度であれば、リハビリや生活習慣の見直しで改善が期待できます。物理療法(温熱・電気療法)、ストレッチ、姿勢改善トレーニングなどが中心です。重症の場合には、神経ブロック注射やごく稀に手術が検討されることもあります。
3. 自宅でできる胸郭出口症候群の運動法
3-1. 肩甲骨まわりのストレッチ3選
肩甲骨周囲の柔軟性を高めることで、神経や血管の圧迫を軽減できます。おすすめのストレッチには以下の3つがあります。①肩甲骨を寄せる「肩甲骨寄せ体操」②壁を使った「胸を開くストレッチ」③タオルを使って背中を伸ばす「タオルストレッチ」。これらは1日5〜10分ででき、デスクワークの合間にも取り入れやすいのが特長です。無理せず、呼吸を意識しながら行うことがポイントです。
3-2. 姿勢改善に効果的なエクササイズ
姿勢の乱れが胸郭出口症候群を悪化させるため、エクササイズによる姿勢改善は欠かせません。とくに重要なのは背筋(脊柱起立筋)と腹筋のバランスです。ドローイン(腹式呼吸による体幹強化)や、猫背改善エクササイズ(背中の伸展運動)を毎日続けることで、正しい姿勢が保ちやすくなります。少しずつコツコツやっていく事をお勧めします。
より個人に合わせたストレッチやマッサージを受けたい方は、当院にご予約を!
4. 状態改善を成功させるポイント
4-1. 痛みがあるときに避けるべき動きと姿勢
運動中に注意すべきなのが、「症状を悪化させる動作」です。たとえば、腕を長時間上げた状態、重たい荷物を肩にかける、または猫背姿勢は避けるべきです。痛みやしびれが強まるようであれば、その運動はすぐに中止してください。無理に動かすことは逆効果となる可能性があります。症状の軽快とともに、徐々に可動域を広げていくことが、長期的な改善に繋がります。
4-2. 継続するための習慣化テクニック
運動の効果を得るには、継続が最も大切です。習慣化のコツとしては、「時間と場所を決める」「無理のない目標設定」「記録をつける」などが有効です。たとえば、朝起きてすぐや夜の入浴後にストレッチを取り入れると、日課として定着しやすくなります。アプリでリマインド設定をしたり、紙に記録を残すのもおすすめ。3週間続けることで、自然と習慣になっていきます。
5. いつ病院に行くべき?受診の目安と注意点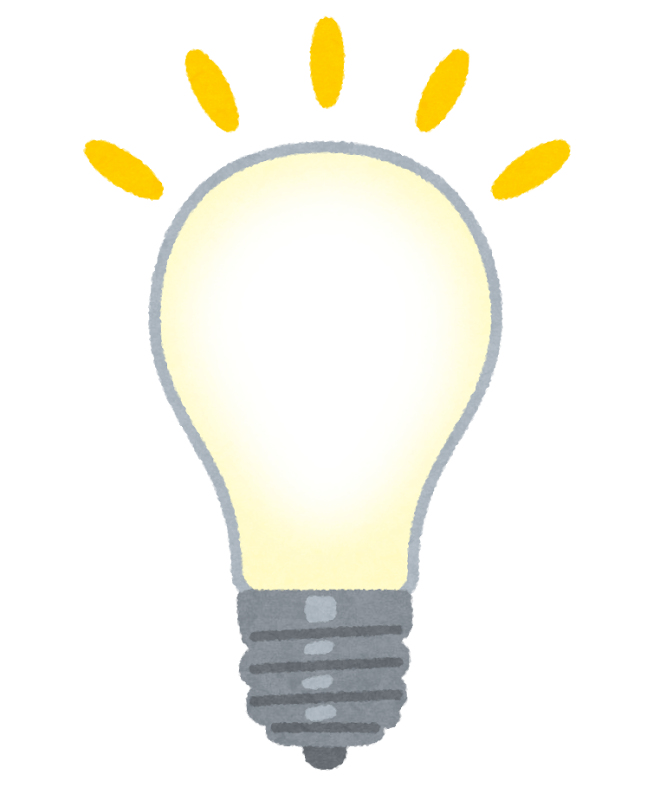
5-1. 自宅の運動で改善しないときのサイン
自宅での運動を続けても「しびれが悪化する」「夜間痛で眠れない」「日常動作に支障が出る」などの症状がある場合は、自己判断せず医療機関を受診しましょう。神経や血管への圧迫が進行している可能性があります。
5-2. 整形外科・リハビリ科での具体的な治療法
医療機関では、まず正確な診断に基づき、患者の症状に応じた治療が行われます。整形外科では、物理療法や鎮痛薬、ブロック注射などを組み合わせることが一般的です。リハビリ科では、理学療法士による専門的な運動療法や姿勢指導が受けられます。医師とリハビリスタッフが連携しながら進めるため、より的確かつ安全に改善を目指すことができます。
【まとめ】
胸郭出口症候群は、神経や血管が圧迫されて腕や手にしびれ・痛みが出る疾患で、早期対処が重要です。
主な原因は姿勢の崩れや筋肉の緊張であり、日常生活の動作や習慣が大きく関係しています。
自宅でできるストレッチやエクササイズを継続することで、症状の軽減・再発予防が期待できます。
痛みが強いときは無理をせず、悪化させない工夫と習慣化がリハビリ成功のカギになります。
症状が長引く、または悪化する場合は、整形外科やリハビリ科を早めに受診しましょう。
【ご来院を検討中の方へ】
- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!
- 荒川沖駅から徒歩1分|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)
- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利
当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース
【簡単2ステップ予約】
- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます
- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。
また、当院インスタグラムでは様々なストレッチ・筋トレ方法をご紹介していますのでそちらもご活用ください!
当院インスタグラム:Instagram



