繰り返す捻挫を防ぐ!バスケットボール選手のための治し方と再発防止トレーニング
- 2025年11月15日
- カテゴリー:運動

バスケットボールでは、ジャンプ着地や急な方向転換によって足首の捻挫が起こりやすく、一度捻挫すると「クセになる」と感じる選手も少なくありません。しかし、正しい治し方と予防トレーニングを実践することで、再発リスクは大きく減らせます。本記事では、バスケットボール選手に多い捻挫の原因、効果的な治療方法、そして再発を防ぐためのトレーニングまで、分かりやすく解説します。早期復帰だけでなく、ケガを繰り返さない身体作りを目指しましょう。
【目次】
1. バスケットボールで捻挫が起こりやすい理由
- 1-1 バスケ特有の動きが足首に与える負担
- 1-2 捻挫を繰り返してしまうメカニズム
2. 捻挫した直後に行うべき正しい応急処置
- 2-1 RICE処置の正しい手順と注意点
- 2-2 やってはいけないNG行動とは?
3. 捻挫を早く治すためのセルフケアと治療方法
- 3-1 回復を早める固定・アイシングのポイント
- 3-2 炎症が落ち着いた後に行う可動域改善ストレッチ
4. 再発を防ぐためのトレーニング
- 4-1 足首周りの筋力強化メニュー
- 4-2 バランストレーニングで「崩れない軸」を作る
5. バスケに安全復帰するためのステップ
- 5-1 練習復帰前にチェックすべき5つの動作
- 5-2 テーピング・サポーターの賢い使い方
1:バスケットボールで捻挫が起こりやすい理由
1-1 バスケ特有の動きが足首に与える負担
バスケットボールでは、ジャンプからの着地、急停止、切り返しなど、足首に瞬間的な負荷がかかる動作が連続します。特に片足での着地や相手との接触がある場面では、足首が内側に大きくひねられやすく捻挫のリスクが高まります。こうしたプレーの特性上、足首周囲の筋力やバランス能力が十分でないと、不安定な状態でプレーし続けることになり、ケガを誘発しやすくなります。
1-2 捻挫を繰り返してしまうメカニズム
捻挫後に靭帯が緩んだままだと、足首を支える安定性が低下し、軽い接触や方向転換でも再びひねりやすくなります。また、痛みが軽減したからといって復帰を急ぐと、筋力や可動域が不十分なままプレーすることになり再発しやすい状態に。さらに、足首周りの感覚機能(固有感覚)が低下することで、無意識の姿勢制御が弱くなり、捻挫を繰り返す「クセ」が形成されるのです。
2:捻挫した直後に行うべき正しい応急処置

2-1 RICE処置の正しい手順と注意点
捻挫直後は、安静(Rest)・冷却(Ice)・圧迫(Compression)・挙上(Elevation)のRICE処置が基本です。痛みが強い場合は無理に動かさず、まず冷却で炎症を抑えます。アイシングは1回15~20分を目安に行い、凍傷を避けるため直接氷を当てないよう注意します。圧迫と挙上は腫れの拡大を防ぐために重要で、早期に実施するほど効果的です。適切な初期対応が、その後の治りの早さを大きく左右します。
2-2 やってはいけないNG行動とは?
捻挫直後に温めたり、マッサージを行ったりすると炎症が悪化し、腫れが増える可能性があります。また、「少し痛いけど動けるから大丈夫」とプレーを続けるのは最も危険な行動です。靭帯の損傷が進むことで治癒が遅れ、再発のリスクが高まります。正しい処置と安静を優先し、無理な動作を控えることが回復の鍵になります。
3:捻挫を早く治すためのセルフケアと治療方法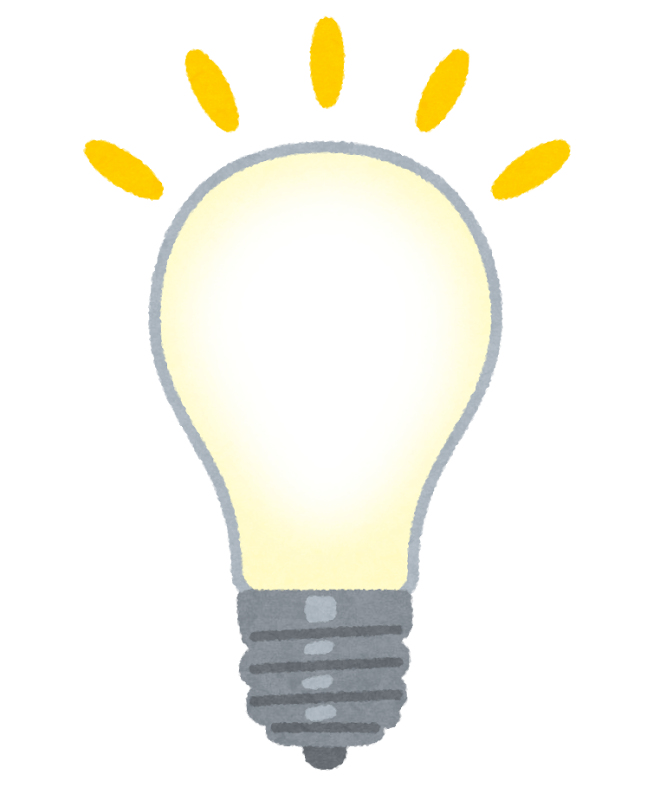
3-1 回復を早める固定・アイシングのポイント
炎症期が落ち着くまでの数日は、テーピングやサポーターで適度に固定し、足首の動きを制限することが重要です。安定性を確保しながら歩行することで、無駄な負荷を避け回復を促します。また、痛みや腫れが残る場合は継続してアイシングを行い、炎症の再拡大を防ぎます。固定は必要以上にきつくしないことがポイントで、血流が悪くなると治りが遅くなるため注意しながら調整します。
3-2 炎症が落ち着いた後に行う可動域改善ストレッチ
痛みが軽減してきたら、足首の可動域を取り戻すためのストレッチを開始します。つま先を上下に動かす運動や、円を描くように回す動作は、負担が少なく関節の動きを改善するのに効果的です。また、アキレス腱やふくらはぎのストレッチを併せて行うことで足首全体の柔軟性が向上し、再発防止にも役立ちます。無理をして痛みが出るほど伸ばすのではなく、心地よい範囲で継続することが大切です。
ストレッチ初心者はこちらのブログもチェック✅
初心者必見!ストレッチの基本と正しいやり方を徹底解説【完全ガイド】 | 荒川沖姿勢改善整体アース
4:再発を防ぐためのトレーニング
4-1 足首周りの筋力強化メニュー
足首の安定性を高めるには、腓骨筋や後脛骨筋などの足首を支える筋肉の強化が欠かせません。チューブを使った足の外向き・内向きのトレーニングや、タオルを足指で引き寄せる運動など、シンプルでも効果的なメニューが多数あります。特に外側の筋肉を鍛えることで内反捻挫を防ぐ効果が高まります。
4-2 バランストレーニングで「崩れない軸」を作る
捻挫の再発防止には、筋力とともにバランス能力を高めることが不可欠です。片足立ちでのキープや、バランスディスクを使ったトレーニングは、足首周りの細かな筋群を活性化させ、無意識に体を支える力を向上させます。最初は両足で行い、慣れてきたら片足・目を閉じるなど負荷を調整すると効果的です。バランス能力が上がると、着地時や接触時でもブレにくい「安定した軸」を身につけられます。
身体の使い方を詳しく知りたい方は、当院でも姿勢サポートをすることが出来ますので体験してみてはいかがでしょうか?
5:バスケに安全復帰するためのステップ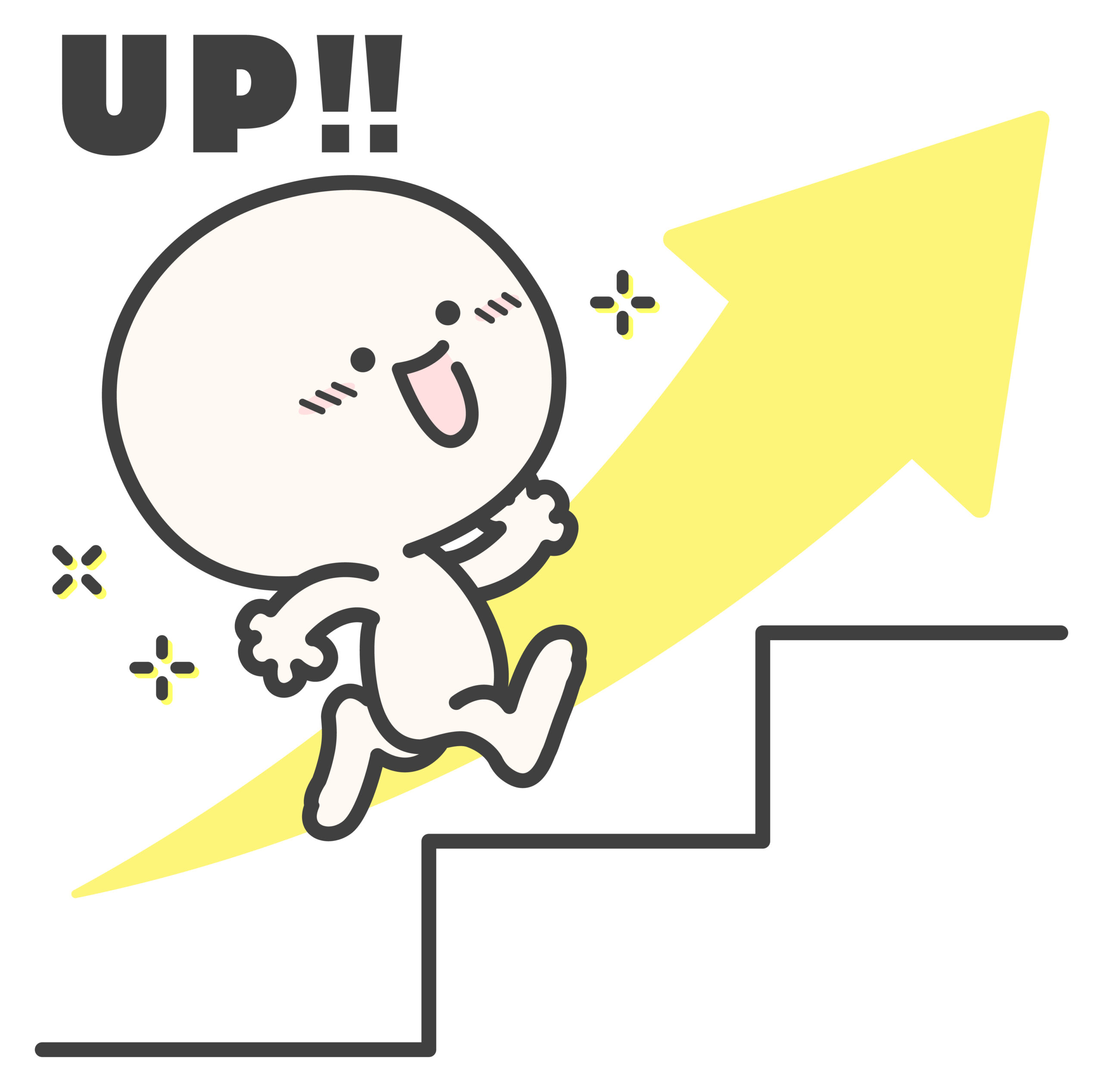
5-1 練習復帰前にチェックすべき5つの動作
復帰前には、ジャンプ・片足スクワット・サイドステップ・ダッシュ・急停止の5つの動作を痛みなく行えるか確認しましょう。これらはバスケ特有の動作に直結しており、問題なくこなせるかどうかで足首の回復度合いが判断できます。どれか1つでも痛みや不安定感がある場合は、無理に復帰すると再発につながりやすく危険です。焦らず段階的に負荷を上げ、確実に回復を積み重ねることが重要です。
5-2 テーピング・サポーターの賢い使い方
復帰直後は足首の安定性が万全とは限らないため、テーピングやサポーターで補助するのが有効です。テーピングは関節の動きを制限しつつ、プレーの感覚を損なわない点がメリット。一方、サポーターは着脱が簡単で練習中も使いやすい利点があります。ただし、長期間頼りすぎると筋力が低下する可能性があるため、あくまで「一時的な補助」として活用し、並行してトレーニングを続けることが理想です。
【まとめ】
〇バスケットボールでは動きの特性上、足首に負荷がかかり捻挫が起こりやすく、一度のケガが再発リスクを高める
〇捻挫直後はRICE処置を正しく行い、温める・動かす・プレーを続けるなどのNG行動を避けることが重要
〇炎症が治まったら、可動域改善ストレッチと適度な固定で回復を促し、痛みのない範囲で動作を戻していく
〇再発防止には、足首周囲の筋力強化とバランストレーニングを継続し、安定した軸を作ることが不可欠
〇復帰前には5つの動作テストとテーピング・サポーターの適切な使用で安全性を高め、無理のない復帰を目指す
【ご来院を検討中の方へ】
- 完全予約制|じっくり対応。待ち時間ほぼなし!
- 荒川沖駅から徒歩1分、阿見町在住の方もアクセスしやすい!|荒川沖駅東口ロータリー内のビル2回(目利きの銀二さんの2つ隣のビルの2階)
- 平日夜20時まで営業|仕事帰りにも便利
当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース
【簡単2ステップ予約】
- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます
- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。
また、当院インスタグラムではストレッチ方法などもご紹介していますのでそちらもご覧ください!
当院インスタグラム:Instagram



