離断性骨軟骨炎の初期症状とは?見逃しがちなサインに注意!
- 2025年07月12日
- カテゴリー:関節痛
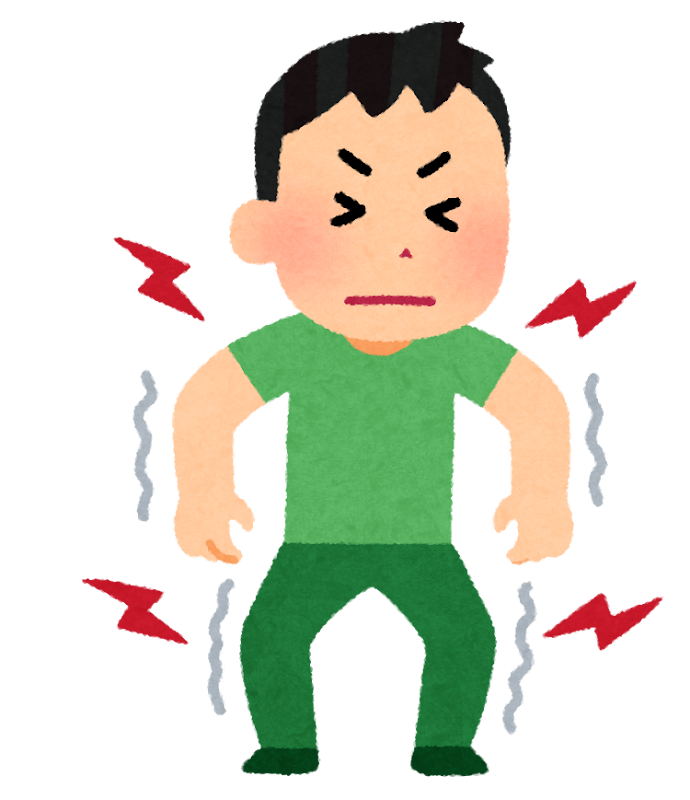
離断性骨軟骨炎(OCD)は、主に成長期の子どもやスポーツをする若者に多く見られる骨と軟骨の障害です。初期の段階では自覚症状が少なく、気づかずに悪化するケースも少なくありません。この記事では、離断性骨軟骨炎の初期症状や見逃しやすいサインをわかりやすく解説します。早期発見のポイントや、保護者・指導者が気をつけるべきチェックポイントもご紹介します。
目次
1. 離断性骨軟骨炎とはどんな病気?
1-1 離断性骨軟骨炎の定義と原因
骨と軟骨の一部が血流障害により壊死する仕組み
1-2 好発年齢と発症しやすい部位
膝・肘・足首などスポーツで酷使する部位が多い
2. 初期症状を見逃さないために
2-1 痛みの特徴と現れ方
運動後に出る鈍い痛み、安静で軽減する傾向
2-2 運動パフォーマンスの低下に注意
無意識の動きの変化やフォームの乱れもサイン
3. 見逃しやすいサインとは?
3-1 子どもの「だるい・疲れた」は要注意
疲労と混同しやすい症状の実態
3-2 腫れ・引っかかり感・可動域の変化
関節の違和感や引っかかり感がヒントになる
4. 早期発見が大切な理由
4-1 初期治療で手術回避できる可能性も
保存療法で回復が期待できるゴールデンタイム
4-2 放置した場合のリスクと後遺症
離断や関節内遊離体(関節ねずみ)への進行
5. 早期発見のためにできること
5-1 保護者・指導者が気をつけたいポイント
休養・チェック・整形外科の受診タイミング
5-2 病院での検査方法と診断の流れ
レントゲンやMRIによる診断の重要性
1. 離断性骨軟骨炎とはどんな病気?
1-1 離断性骨軟骨炎の定義と原因
離断性骨軟骨炎(Osteochondritis Dissecans/OCD)は、関節内の骨とその表面の軟骨が血流障害によって壊死し、剥がれてしまう疾患です。はっきりとした原因は不明ですが、繰り返される微細な外傷や過度な運動、成長期における骨の未成熟さが影響すると考えられています。スポーツをしている子どもや若年層に多く見られ、発見が遅れると関節機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
1-2 好発年齢と発症しやすい部位
発症しやすい年齢は10~15歳の成長期。骨の形成が不安定な時期に激しい運動を行うとリスクが高まります。特に膝(大腿骨顆部)や肘(上腕骨小頭部)、足首(距骨滑車)など、スポーツで酷使されやすい部位に発症するケースが目立ちます。体の負担が集中しやすい部位ほど注意が必要です。
2. 初期症状を見逃さないために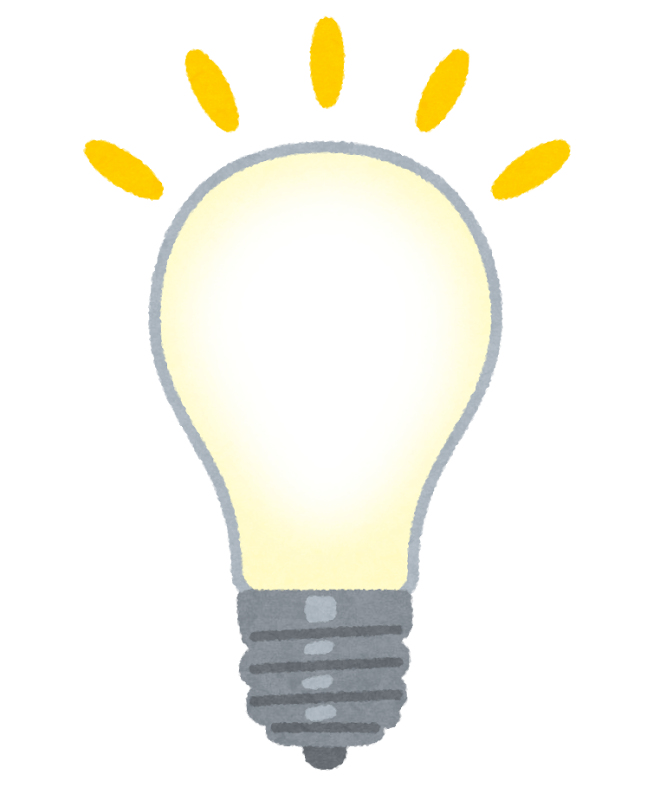
2-1 痛みの特徴と現れ方
離断性骨軟骨炎の初期では、痛みは軽度で不定期に現れることが多く、特に運動後に「うずくような鈍い痛み」を訴えるケースが目立ちます。安静にしていると軽快するため、単なる筋肉疲労と勘違いされやすいのが特徴です。痛みの部位がいつも同じで、何度も繰り返すようであれば要注意です。
2-2 運動パフォーマンスの低下に注意
プレー中の「切れ」や「安定感」がなくなってきた、ジャンプや投球のフォームが崩れてきたと感じた場合、それは初期症状のサインかもしれません。本人が気づかないまま無意識にかばっていることもあり、周囲が早期に変化を察知することが重要です。慢性的な違和感や調子の悪さが続く場合は整形外科の受診をおすすめします。
3. 見逃しやすいサインとは?
3-1 子どもの「だるい・疲れた」は要注意
子どもは痛みや違和感をうまく言葉にできないことが多く、「なんとなくだるい」「疲れが取れない」などの曖昧な表現で訴えることがあります。こうした言葉は成長や日々の運動の一部と捉えられがちですが、実は離断性骨軟骨炎の初期症状である可能性もあります。休ませても改善しない場合は注意が必要です。
3-2 腫れ・引っかかり感・可動域の変化
関節の腫れ、動かす際の「引っかかり感」、可動域の減少といった変化も見逃せないサインです。とくに関節の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなった、動かすとゴリゴリする、といった訴えがあれば、関節内で骨や軟骨の異常が進行している可能性があります。放置せず、早めの医療機関受診が望まれます。
4. 早期発見が大切な理由
4-1 初期治療で手術回避できる可能性も
離断性骨軟骨炎は早期に発見し、適切な保存療法(安静、運動制限など)を行うことで、手術せずに自然治癒するケースもあります。とくに骨がまだ成長段階にある子どもでは、自然修復力が高いため、早期対応がカギとなります。無理を続けると治癒が難しくなり、治療の選択肢が狭まってしまいます。
4-2 放置した場合のリスクと後遺症
初期症状を見過ごして進行すると、軟骨や骨の一部が関節内で剥がれ関節内の変形などに繋がる可能性もあります。重症化すると保存療法では回復が難しくなり、手術が必要になることもあります。
5.早期発見のためにできること
5-1 保護者・指導者が気をつけたいポイント
子どもや選手が「何となく違和感がある」と言ったら、無理に練習を続けさせずに、まずは休養を取らせましょう。練習日誌やパフォーマンスの記録をつけることで、微妙な変化にも気づきやすくなります。保護者や指導者が、本人より先に「異変」に気づくことが、早期発見の第一歩です。
5-2 病院での検査方法と診断の流れ
整形外科では、まず問診・触診のあと、X線(レントゲン)撮影で骨の状態を確認します。早期では異常が写りにくい場合もあり、必要に応じてMRI検査を行うことがあります。MRIでは軟骨や骨の内部の変化も詳しく見られるため、確定診断や治療方針の決定に有用です。違和感を感じたら早めに受診しましょう。
【まとめ】
・離断性骨軟骨炎は、10~15歳の成長期におこる軟骨が何らかの影響で剥がれる炎症
・早期に安静・治療をすることが大切である
・診断は、レントゲンでは足りない事もあるため、MRIでの検査が必要となる場合もある
いかがでしたでしょうか?
私が担当した方では、小学生・中学生ともに重症な状況の子が多く治癒となるまで1年を要する子もいました。本来荷重量の制限なども設けている医師もいらっしゃるかと思いますが、本人が荷重量を守れない場合があります。そうすると長引くといった悪い循環となるので、親御さんと本人とのコミュニケーションが大切になるケガであると思います。
直接には施術をすることは出来ないので、患部以外で体の使い方を理解することが大切となりますので、もし興味がありましたら一度当院にいらしてもらって体の使い方を学んでみてはいかがですか?
当院予約ページ:WEB予約│荒川沖駅徒歩1分の荒川沖姿勢改善整体アース
【簡単2ステップ予約】
- ご希望の時間を選択し、情報の入力をしていただきます
- 送信後、当院から当日の流れに関するメールが届きますのでご確認をお願い致します。
当院インスタグラムでは、ストレッチ方法・筋トレ方法なども発信していますので、是非ご活用ください。
当院インスタグラム:Instagram



